キヤノンメディカルシステムズ,「50年の時を超えて,CT新時代へ」をテーマに「Global Standard CT Symposium 2025」を開催
2025-8-28

「50年の時を超えて,CT新時代へ」を
テーマに掲げた
「Global Standard
CT Symposium 2025」
キヤノンメディカルシステムズ(株)は,2025年8月23日(土),「Global Standard CT Symposium 2025」をオンラインで開催した。本シンポジウムは,同社CTの最先端技術や最新の臨床知見を共有することを目的に毎年開催されている。14回目となった今回は,「50年の時を超えて,CT新時代へ」をテーマに6演題が設けられ,同社CTの開発の歴史や最新CTの臨床的有用性,画像再構成技術の進歩などが報告された。なお,今回は,事前登録者数が1500名を超えたことが発表され,同社CTへの注目度の高さがうかがえた。
冒頭の挨拶で,代表取締役社長の瀧口登志夫氏は,今年はX線CTが日本で臨床稼働を開始してから50年の記念の年であると述べた。同社の前身である東芝社が1975年に国内第1号機を導入して以降,同社ではCTの開発を強力に推進し,患者の負担および被ばくの低減と,精度の高い診断に寄与する技術の開発に取り組んでいる。瀧口氏は,320列Area Detector CT(ADCT)「Aquilion ONE」をグローバルスタンダードCTとして世界に普及させることをめざすとともに,高精細CTや全身用マルチポジションCTといった革新的な装置の開発や,Deep Learning Reconstruction(DLR)による画質向上と被ばく低減の両立などを実現してきたと強調した。また,フォトンカウンティングCT(PCD-CT)の早期実用化に務めるとともに,画像診断技術のさらなる発展に寄与していくとの抱負を語った。
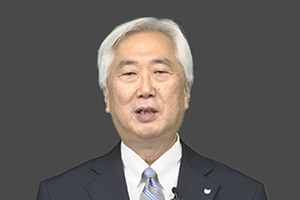
瀧口登志夫氏(代表取締役社長)
続いて,同社CTユーザーである6名のエキスパートによる講演が行われた。座長は広島県立病院機構の粟井和夫氏と岩手医科大学の吉岡邦浩氏が務めた。
大原綜合病院の森谷浩史氏は,「国内CT導入50年 CTがもたらす胸部画像診断の進展」と題して講演した。森谷氏は,CTの黎明期から45年にわたり肺がん診療に携わってきた経験を踏まえ,CTの技術的進歩が肺がんの画像診断に貢献してきた経緯などを概説した。なかでも,肺を鮮明に描出可能な装置として,高精細CT「Aquilion Precision」を挙げたほか,Aquilion Precisionの高精細画像を教師として開発されたDLRである「Precise IQ Engine(PIQE)」では,Aquilion ONEの画像を容易に高精細化でき,臨床での実用性に優れた技術であると述べた。また,deep learningを応用した動き補正技術「CLEAR Motion」を用いることで,心拍動の影響による画像のブレが大幅に抑制されるとして,肺野領域における有用性を示した。

座長:吉岡邦浩氏(岩手医科大学:左),粟井和夫氏(広島県立病院機構:右)

森谷浩史氏(大原綜合病院)
琉球大学大学院の與儀 彰氏は,「Deep learningで脳血管と中内耳のディープな部分を映し出す」と題して講演した。Aquilion Precisionで撮影した頭部CTAでは,脳の血管を末梢まで明瞭に描出可能であることを,物理評価や視覚的評価の結果および症例画像を示して報告した。また,空間分解能を維持したままノイズを選択的に除去するDLRの「Advanced intelligent Clear-IQ Engine(AiCE)」をAquilion Precisionの画像に適用することで,ノイズに埋もれた微細な血管をより明瞭に描出可能になるとし,術前のシミュレーション画像の精度向上に貢献すると述べた。さらに,AiCEを適用した画像では,中内耳の微細構造もより明瞭に描出できるため,手術時の合併症の頻度を低減できる可能性があると示唆した。

與儀 彰氏(琉球大学大学院)
高瀬記念病院の佐野始也氏は,「新世代のAquilion ONEとDLR技術は冠動脈CT検査を変える!」と題し,最新のADCTである「Aquilion ONE / INSIGHT Edition」を用いた冠動脈CT検査の実際などを報告した。Aquilion ONE / INSIGHT Editionは,ガントリ回転速度が0.24s/rotへと高速化したことに加え,PIQEやCLEAR Motion,人工知能(AI)を活用した自動化技術などの搭載によって,心臓検査の適応拡大に寄与する装置となっている。佐野氏は,複数の画像再構成法を比較した物理評価の結果を示して,PIQEは空間分解能,ノイズ特性共に優れているとしたほか,線量を1/4に低減しても既存の画像再構成法と同等以上の結果が得られると説明。症例画像を供覧し,血管内ステントなどを明瞭に描出可能であることを示した。さらに,CLEAR Motionを適用することで高心拍症例においてもモーションアーチファクトが改善し,拡張中期位相が最良となる場合が多く見られるなど,有用性が高いと述べた。
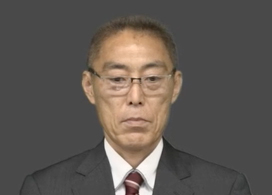
佐野始也氏(高瀬記念病院)
奈良県立医科大学の南口貴世介氏は,「高精細画像がもたらす,IVR治療へのインパクト」と題して,Aquilion ONE / INSIGHT Editionに搭載されたdeep learning応用技術であるPIQEとdual energy CT技術「Spectral Imaging System」の有用性を中心に報告した。IVRの治療プランニングにおいて術前CTはきわめて重要であるとした上で,IVRの観点からPIQEの特長を紹介。特にPIQEの1024マトリックスの画像では,血管が末梢まで明瞭に描出されることから,術前画像評価の精度を高め,治療戦略において真価を発揮しうると評価した。また,dual energy CTでは,取得した画像データを基にヨードマップや実効原子番号画像,電子密度画像などが得られる。南口氏はこれらのうち電子密度画像を挙げ,薬剤溶出ビーズを用いた肝動脈化学塞栓療法(DEB-TACE)などの治療後の評価に用いることで,治療効果を早期に予測できる可能性があると述べた。

南口貴世介氏(奈良県立医科大学)
国立がん研究センター東病院の久野博文氏は,「頭頸部癌の画像診断におけるフォトンカウンティングCTのポテンシャル—臨床現場でどう使われるか?—」と題して,同社製PCD-CTのプロトタイプ1号機の使用経験を報告した。久野氏は,PCD-CTについて,高空間分解能化とコントラスト向上を同時に実現し,かつマルチエネルギースペクトラル画像を提供する次世代万能型CTであると説明。その上で,頭頸部がん精査における同院のPCD-CTの撮影法を紹介し,高精細画像とスペクトラル画像の併用が診療に有効であった症例を提示した。また,頭頸部がんの画像診断における客観的指標として,画像的リンパ節外浸潤の評価の重要性が高まっていることを挙げ,PCD-CTとDLRによって浸潤の程度を明瞭化することで診断の不確実性を軽減できるとの期待を示した。

久野博文氏(国立がん研究センター東病院)
本シンポジウムの最後には,慶應義塾大学の陣崎雅弘氏が,「マルチポジションCT(Aquilion Rise)の開発と導入〜From Medicine to Healthcare〜」と題して講演した。全身用マルチポジションCT「Aquilion Rise」は,世界初(同社調べ)の臥位,立位,座位での撮影が可能なCT装置。慶應義塾大学医学部放射線科学教室との産学連携によって共同開発され,2025年4月に販売が開始された。超高齢化社会において健康長寿を実現するためには,器質的疾患の評価はもとより,機能性疾患の評価が重要となるが,従来の臥位CTでは立位で症状が出現する疾患を評価することは困難である。陣崎氏は,そのような開発の背景や経緯を述べた上で,立位CTが有用であった症例を多数提示し,今後は健康寿命を評価するための画像診断学を構築していきたいと述べた。また,現在,米国などでは重粒子線治療において座位照射の開発が進んでいることから,治療計画における座位CTの必要性や有用性が高まっていくと展望した。

陣崎雅弘氏(慶應義塾大学)
●問い合わせ先
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
広報室
https://jp.medical.canon
