Philips INNOVATION and VALUE(フィリップス・ジャパン)
2025年8月号
Angio Talk about the Future
「Direct to Angio Suite」で脳卒中診療を迅速化し患者と家族,そして日本の医療の未来を守る
日本における脳卒中は近年,国の政策や医療技術の進歩により治療成績が向上したが,後遺症による長期的なケアが必要になるなど課題がある。今後,高齢化による患者の増加と生産年齢人口減少による医療現場の人材不足が進む中で,これからの脳卒中診療には何が求められるのか。Royal PhilipsのChief Medical OfficerのAtul Gupta氏が,日本の医療政策・行政にかかわってきた畦元将吾氏,島井健一郎氏と意見を交わした。
Talk1
畦元将吾 氏(自由民主党参議院比例区支部長,前・衆議院議員) × Atul Gupta 氏(Chief Medical Officer, Royal Philips)

畦元将吾 氏(左)
診療放射線技師として病院勤務,医療機器メーカーの経営者を経て,2019年に衆議院議員初当選。2022年から第二次岸田改造内閣において厚生労働大臣政務官を務めた。
Atul Gupta 氏(右)
Image Guided Therapy(IGT)など全診断・治療事業を統括する。インターベンションと画像診断の両方の専門医資格を持つ。
革新的な技術の普及に向けてエビデンスを積み重ねることが重要
さらなる効率化が求められる脳卒中診療
Gupta:脳卒中は世界で年間約1200万人が発症し,25歳以上の成人の4人に1人が生涯で経験をするとされています*1,2。フィリップスも革新的な診断・治療技術を医療現場に届けられるよう日々努めています。私たちは,Image Guided Therapy(IGT)ソリューションを提供しており,血管撮影装置「Azurion」シリーズの2D・3Dイメージガイダンスは,血栓溶解療法・血栓回収療法による患者回復に寄与しています。これにより死亡数を減少させるだけでなく予後を改善し,介護やリハビリテーションなどの長期的なケアに要するコストの抑制にも貢献しています。
畦元:日本では,これまでも脳卒中の対策に力を入れており,施策を講じてきました。例えば,脳卒中予防の重要性についての教育・啓発です。脳卒中を防ぐために健康診査を勧奨し,健康寿命の延伸を図っています。また,時間との闘いであることから,救急搬送における救急隊員の救護活動のための体制整備も進めてきました。さらに,急性期脳卒中のための医療機関の集約化も行ってきました。一方で,リハビリテーションや介護の人材は不足しており,効率化が課題となっています。
ワンストップショップを実現する「DTAS」
Gupta:さらなる効率化に向けてフィリップスでは,デジタル技術を活用したソリューションの提供を加速しています。その一つとして,Direct to Angio Suite(DTAS)を提唱しています。DTASは,患者が救急搬送された際にCT撮影を省略して,脳血管内治療室でAzurionによる「SmartCT」と呼ばれるコーンビームCT(CBCT)撮影を施行し,速やかに診断を行い,治療に移行します。これにより時間短縮を図るワンストップショップソリューションです。フィリップスが後援する多施設共同研究「WE-TRUST」のランダム化比較試験において,16の医療施設で約500症例ほど集積し,DTASにより45〜60分程度の時間短縮を実現できていることを確認しました*3。さらに,予後も改善し,後遺症の低減も図れています。2025年に新病院が開院した大阪けいさつ病院でも運用が始まり,良い評価を得ています。
畦元:非常にすばらしい技術ですが,DTASを日本に普及させるには,診療報酬での評価が必要です。それには日本国内でのデータを収集して,エビデンスを積み重ねることが重要です。
Gupta:診療報酬も含め,コストは重要なテーマです。DTASにより予後を改善できれば,ICUの滞在期間や在院日数を短縮し医療機関経営につながるメリットも多く,また,リハビリテーションや介護のコストを削減することができ,日本の社会保障費の増加を抑えることにもなります。さらに,人材などの医療資源をほかの疾患の診療に再配分することも期待できます。
畦元:予後が改善すれば社会復帰がしやすく,発症前と同じ仕事を続けられる可能性も高いので,患者のQOLの向上だけでなく,人手不足が深刻化する社会全体にとっても価値があります。また,社会保障費の伸びの抑制につながります。
革新技術の普及に期待
Gupta:フィリップスは「2030年までに年間25億人の人々の生活を向上させる」ことをパーパスに掲げており,日本でもDTASで多くの人の命を救いたいと考えています。畦元先生には政治家の立場から,患者を救う活動をしていただきたいです。
畦元:私の政治家としてのポリシーの一つは,「寝たきりの人を極力少なくする」ことです。これは患者と家族の経済的な負担を軽減し,幸福につながります。それを実現するためにも,脳卒中診療の早期診断・治療は重要であり,DTASのような革新的な技術が普及することを期待しています。
(2025年3月19日取材)
*1 World Stroke Organization(WSO) : Global Stroke Fact Sheet 2025.
*2 Global Burden of Disease 2021 Study. Lancet Neurol., 23(10) : 973-1003, 2024.
*3 https://www.wetrust-study.com/#we_trust_study
Talk2
島井健一郎 氏(滋慶医療科学大学医療科学部教授 / 厚生労働省健康・生活衛生局参与) × Atul Gupta 氏(Chief Medical Officer, Royal Philips)
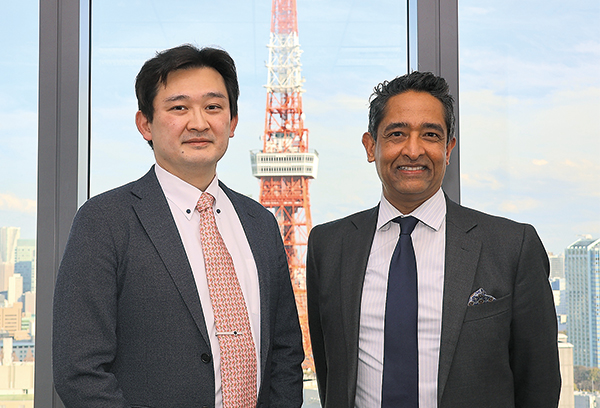
島井健一郎 氏(左)
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)経営審議委員会委員,慶應義塾大学SFC研究所上席所員,メディカルデザイン総合研究所代表・所長を務める。厚生労働省の参与として,医療DXや地域保健・健康行政における情報化などの施策にかかわっている。
医療の課題解決に向け地域社会システムのインテグレータに
医療従事者のバーンアウトは共通の課題
Gupta:現在,世界中の多くの国々が,医療における共通の課題を抱えています。1つは高齢化に伴う重症化と疾病の複雑化です。医療の進歩により寿命は飛躍的に伸びましたが,一方で,慢性疾患や認知症を抱える状況になっています。2つ目の課題は,1つ目の課題がもたらした医療従事者の業務量の増加と人手不足です。患者が増え,業務量の増加に伴って,医師や看護師のバーンアウト(燃え尽き症候群)が深刻化しています。フィリップスは,AI技術やロボット,遠隔医療などのデジタル技術を用いたソリューションを提供して,これらの課題解決に挑んでいます。
島井:日本もバーンアウトを防ぐために,医師の働き方改革などが施行されています。さらに,国を挙げて医療DXを推進し負担軽減が図られています。第217回通常国会では,「医療法等の一部を改正する法律案」が提出され,医療DXの推進のための法令改正が進められています。本法案は,地域医療構想の見直し,医師偏在是正に向けた総合的な対策も盛り込まれています。
医療資源の有効活用にも寄与する「DTAS」
島井:新たな地域医療構想では,医療機関の機能の報告制度を設けるなど,地域全体での医療提供体制を明確にすることが求められます。例えば,脳卒中診療では,地域全体での診療プロセスを示して整備していくことになります。
Gupta:脳卒中は全世界で大きな問題であり,患者数が増加していますが,IGTによる低侵襲な血栓回収療法を施行でき,患者の負担を軽減できます。しかし,世界ではこのような治療にアクセスできる患者がまだ少数に限られています。日本は,1970年代に脳卒中が死因の1位でしたが,国を挙げて対策した結果現在は4位になり,脳卒中診療の先進国だと言えます*1。ただし,私は日本もさらなる取り組みが必要だと考えています。
島井:地域全体での脳卒中診療の体制を整備して,そこにITなどのデジタル技術を活用して,質の向上と効率化を図っていくことが求められます。現在,進行している「全国医療情報プラットフォームの構築」といった医療DXの推進などによって情報共有・連携が進むことで,脳卒中診療がより良くなるはずです。
Gupta:フィリップスでは,脳卒中診療におけるペイシェント・ジャーニーでのワークフローに焦点を当てたソリューションを開発,提供しています。一貫したプロセスを構築することで,アウトカムを改善できると考えています。そのソリューションの一つが,血管撮影装置「Azurion」シリーズを用いたDirect to Angio Suite(DTAS)です。脳卒中診療を迅速化することで,患者の予後改善および社会復帰を早めることにつながり,経済的な負担の軽減に寄与します。医療機関にとってもコストを抑制するだけでなく,人材不足の解消につながります。さらに,地域全体から見ても,限られた医療資源の有効活用につながるはずです。
地域社会システムのインテグレータに
島井:救急搬送から診断,治療,リハビリテーション,介護まで,地域全体でワークフローを改善していくためには,急性期から慢性期までの医療と介護,保健などの事業を担う「地域医療連携推進法人」が重要な役割を担うと考えています。地域医療連携推進法人が地域医療介護総合確保基金を活用して,DTASのような革新的な技術に投資していくことで,医療と介護の質を向上させるだけでなく,地域社会のさまざまな課題解決も図られると期待します。フィリップスにはその中で,地域社会システムのインテグレータとしての役割を果たしてほしいと思います。
Gupta:私たちは,2030年までに全世界の年間25億人の人々の生活を向上させることをパーパスに掲げています。その実現に向けて,日本における地域医療での取り組みを加速していきます。
(2025年3月18日取材)
*1 厚生労働省 : 令和5年(2023)人口動態統計(報告書).
