2021年:AIを活用した撮影の自動化機能などが登場。CTへのAI技術の実装が進む
2025-3-31
AIの技術はさらなる進歩を遂げ,画像再構成のほか,ワークフローの改善に寄与する技術などが登場した。シーメンス社からは撮影の自動化機能「myExam Companion」やAIを活用した画像再構成処理技術「ALPHA(Automatic Landmarking and Parsing of Human Anatomy) Technology」が紹介されたほか,フィリップス社からはAI画像再構成「Precise Image」やAIカメラによる自動ポジショニング「Precise Position」のほか,さまざまなAI技術がCTに実装されたことがアピールされた。
シーメンス社は,2020年4月に発表された「SOMATOM X.cite」がお披露目の場となった。最大のアピールポイントは,AI技術を用いた自動撮影機能によりワークフローの向上を図れることである。代表的な技術が検査ガイド機能の「myExam Companion」で,患者の性別,年齢,体格といった情報の入力のほか,検査目的に応じて用意された質問項目を回答すると,最適なプロトコールが提案される。心臓CTの場合,SOMATOM X.citeが心電図のデータから心拍数,不整脈などを認識。検査者は,カルシウムスコアリング実施やステントの有無といった問いに答えるだけでよい。myExam Companionにより,検査者の技量を問わず,すべてのスタッフ,高品質の画像を撮影できるようになる。一連の操作は,操作室のコンソールと,SOMATOM X.citeのガントリの両サイドにある着脱可能なタブレット端末から容易に行える。セッティングや被検者のポジショニングをベッドサイドでタブレット端末から行い,撮影も操作室に移動せず実施できることから,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の検査にも有用である。さらに,撮影後は,AI技術で開発された「ALPHA(Automatic Landmarking and Parsing of Human Anatomy) Technology」により,MPR画像などの画像再構成や解析処理も自動で行われる。このほかにもオプションとして,被検者のポジショニングを自動化する「FAST 3D Camera」を提供している。FAST 3D Cameraは赤外線カメラを搭載しており,ベッド上の被検者の体厚も含めた体格を立体的にスキャンする。このデータをAIアルゴリズムで解析することで,撮影部位がアイソセンタになるよう自動でポジショニングする。そのため,高精度で位置合わせができ,高画質化に寄与する。これらのAI技術により,CT検査の標準化が図れるとともに,検査時間の短縮が可能となり,医業経営の観点からもメリットを生む。SOMATOM X.citeは,AI技術だけでなく,ハードウエアでもCTとしての優れた基本性能を有している。X線管は,シーメンスヘルスケアのDSCTの最上位機種である「SOMATOM Force」と同じ「Vectron」を採用。最大1.3Aの高出力を得られる。さらに,最新検出器の「Stellarinfinity Detector」を搭載した。このほか,SOMATOMファミリー独自技術である「Tin filter technology」によって,胸部単純CTなら胸部単純X線撮影と同等の被ばく線量で撮影が可能となる。

「myExam Companion」などAI技術で検査を効率化する「SOMATOM X.cite」

「SOMATOM X.cite」はタブレット端末でほぼすべての操作が可能

「FAST 3D Camera」はポジショニングを自動化し高画質とスループット向上に寄与
フィリップス社は,新製品の128スライスCT「Incisive CT Premium」とフラッグシップである「IQon Spectral CT」の最新情報を展示した。Incisive CT Premiumは,2019年に発売した「Incisive CT」にAIソリューション「Precise Suite」を実装した最新のCT装置。“Tube for Life”をコンセプトに開発され,高耐久のX線管球「vMRC」や優れたワークフローが評価されている。Incisive CT Premiumは,AI技術を画像再構成とワークフロー改善の両方に活用している点が特長で,4つの新機能を搭載する。AI画像再構成「Precise Image」は,ディープラーニングによるニューラルネットワークを画像再構成プロセスに採用し,最大80%の線量低減,最大85%のノイズ低減,最大60%の低コントラスト検出能の改善を実現。低線量撮影でもノイズを抑制しながら臓器の辺縁を明瞭に描出することができ,日常診療で利用可能な画像再構成スピードを有する。また,フィリップスのCTには従来から心拍変動に対応した後ろ向き心電図同期アルゴリズムが搭載されているが,Incisive CT Premiumではより高心拍の症例にも対応可能なAI心臓画像再構成「Precise Cardiac」が実装され,冠動脈CTのさらなる画質向上を可能にする。ワークフローにおいては,AIカメラによる自動ポジショニング「Precise Position」が搭載された。天井にカメラを設置して患者の関節を認識することで,体位やセンタリングの状態を判断し,高い精度で一貫性のあるポジショニングを可能にする。従来のポジショニングと比べ,垂直方向精度の50%改善,オペレーター間のバラツキを70%改善,所要時間を23%短縮し,検査数の増加により収益向上にも貢献する。AIを活用したインターベンションサポートツール「Precise Intervention」は,CT画像上で事前に穿刺プランを設定することで,穿刺角度のズレやターゲットまでの距離をリアルタイムに表示する。手技の時間短縮や安全性の向上,経験の浅い医師への教育などにおいて有用となる。一方,二層検出器搭載のIQon Spectral CTは,国内ユーザーからも多くの論文が発表され,臨床的価値が確立されていることをアピールし,仮想単色X線画像(MonoE)の低keV画像による悪性腫瘍の診断能向上や造影剤量の低減,Calcium Suppression画像による微小骨折の早期診断など,ユーザーからの報告を多数紹介した。

AIソリューション「Precise Suite」を実装した「Incisive CT Premium」

AIカメラによる自動ポジショニング「Precise Position」
キヤノンメディカルシステムズ社は,「Aquilion ONE / PRISM Edition」を中心に展示を行った。Aquilion ONE / PRISM Editionは,AiCEやdual energy技術の新たな方式である「Spectral Imaging System」を搭載したADCTのフラッグシップ機。新CT透視システムの操作卓や,キヤノン製のWebカメラと組み合わせて展示された。新CT透視システムは,オプションで提供される生検やドレナージなどCT透視下での手技をサポートするシステム。タッチパネルを採用した操作卓は,寝台やガントリの移動のほか,画面の切り替えなども可能で,術者が穿刺の手技に関する操作を一人で行えるようになっている。展示で提案されたWebカメラソリューションは,キヤノン製のWebカメラを使って,CT室内や撮影時の患者監視用カメラとして利用するもの。キヤノンはネットワークカメラ事業を展開しているが,そのリソースを活用したものだ。そのほか,80列で開口径90cmのラージボアを持つマルチスライスCT「Aquilion Exceed LB」,高精細CT「Aquilion Precision」については,モニタプレゼンテーションで紹介した。Aquilion Exceed LBは,放射線治療計画や救急用として導入されてきたラージボアCTの待望の多列化(80列)装置。高剛性の寝台やAiCEの搭載など,さらなる精度の向上が期待されることをアピールした。

新CT透視システムの操作卓と組み合わせて展示された「Aquilion ONE / PRISM Edition」

タッチパネルを採用した新CT透視システムの操作卓
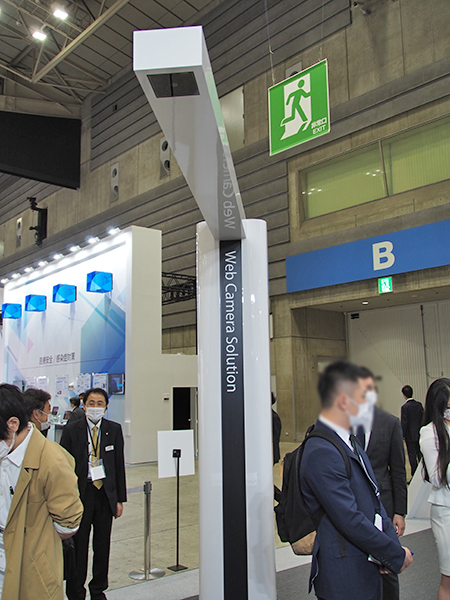
キヤノン製のWebカメラとの組み合わせを提案
富士フイルムヘルスケア社(2021年3月に日立製作所より社名変更)(現・富士フイルムメディカル社)は,64列128スライスCT「SCENARIA View」が新バージョン「phase 3」にアップデートしたことをアピールした。展示されたモックアップは,社名変更に伴って,寝台マットやガントリ脚部のカラーが,シックな富士フイルムカラーに変更された。SCENARIA Viewは,逐次近似処理技術「IPV(Iterative Progressive reconstruction with Visual modeling)」による「低線量と高画質の両立」,高速化・自動化のソリューション「SynergyDrive」による「検査効率の改善」,80cm開口径と横スライド寝台による「快適な検査」をコンセプトに開発された装置。今回リリースされたphase 3は,新設計のフルデジタル検出器の搭載により,「SCENARIA」と比べて電気ノイズの最大40%低減,消費電力の45%低減(Off-time mode機能で最大78%低減),信頼性の向上と30%の軽量化を実現している。また,IPVが進化し,新たに心臓にも適用可能になった。冠動脈CTへのIPV適用により,診断参考レベル(DRLs 2020)の半分程度の線量でも明瞭な画像を得ることができる。心臓CTにおいては,自由度の高い心電図同期連動AECである「IntelliEC Cardiac」や,寝台の横スライドと小視野用Bow-tieフィルタを組み合わせた「IntelliCenter」を併用することで,さらなる被ばくの低減と画質向上を図ることができる。ワークフローを向上させるSynergyDriveについては,撮影範囲の自動設定機能「AutoPose」を,従来の胸部に加えて頭部にも対応するアップデートを行った。OMライン,SMライン,RBラインの基準線をプロトコールにあらかじめ設定しておくことで,スキャノ画像から頭部の撮影範囲を自動認識する。これにより,操作者の作業負担を軽減し,操作者間の設定のバラツキを防ぐことができる。

バージョン「phase 3」にアップデートした64列128スライスCT「SCENARIA View」

新設計のフルデジタル検出器を搭載

逐次近似処理技術“IPV”が心臓にも対応
